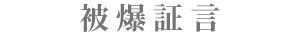
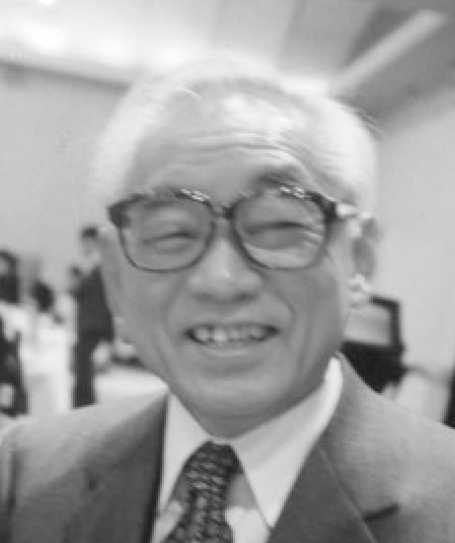
(1932~2020)
証言日:2013年9月1日
私は1944(昭和19)年4月に、観音町の県立広島二中へ入学、自宅のあった牛田町早稲田区から1時間余りを歩いて通学した。その通学途中での忘れられない二つの思い出がある。
一つは通学で横断していた、いまの紙屋町の北側にあった西練兵場で、インテリらしい兵隊さんから小学生の国語教科書の初めにあった「サイタ サイタ サクラガサイタ」を当時は敵国語と言われた英語でいってごらん、と言われてうまく答えられなかったこと。もう一つは、二中へ行くのに遅刻しそうになり、近道をするため、通ることがはばかられた西の遊郭のそばを通り抜けるさい、「石川五右衛門」とあだ名をつけられていた教練担当の配属将校、石川大尉が登楼し、2階の窓から外を見ているのと顔を合わせたことだ。
しかし、なんといっても強烈なのは広島の被爆体験である。
ヒロシマの悲劇のシンボルは、原爆ドームである。私は広島県産業奨励館といわれたドームに、原爆投下の直前に足を踏み入れている。というのは二中の2年生だった私は、原爆投下の前日、8月5日、太田川の川沿いで、産業奨励館のすぐ南側にあたる加古町一帯の家屋取り壊し作業の勤労奉仕をし、その帰りに立ち寄ったのだ。被爆直前の作業とはなんとも間が抜けた話だが、軍都広島は敗戦10日前に、焼夷弾爆撃による延焼防止の空地作りをしていたのである。
その作業を終えての帰り、物好きな私は、奨励館にぶらり入って2階まで上がってみた。用務員さんしかいない館内は、陳列品などは運び出された後で何もなく、運搬用の木枠の残りなどが散乱していた。むろん、翌6日の原爆の惨事も、ドームが原爆のシンボルとなることも露知らず…。私は最後の入館者だったのではないかと思う。
翌8月6日、私たち2年生300人は、いまの広島駅裏にあたる東練兵場で、さつまいも畑の草取り作業をすることになっていた。集合点呼のかけ声で集まりかけていたその時、「米国の爆撃機B29が飛んでいる」と声がして仰ぎ見ている時に、原爆投下に見舞われた。その瞬間、顔や手がヒリヒリと痛み、ちょっと触ると皮膚がすりむけた。顔と両手に火傷を受けたのだ。
私たち2年生はどうやら助かったものの、1年生は同じ6日、前日われわれが作業した加古町のすぐ近くで勤労奉仕していてほとんどが死亡した。太田川の岸のそばに、慰霊碑が立てられている。
東練兵場にいた私は、1人で二葉山の山道を通って、山向こうの牛田町へ戻り、早稲田の自宅へ帰宅した。山道に、回りの樹木の青い葉がたくさん散っていたのを覚えている。
家に帰ってみると、家の戸障子はめちゃくちゃになり、家財道具は散乱して、足の踏み場もないほどだった。そのうち、着のみ着のまま引きちぎれた衣服をまとい、火傷をした人が次々に避難してきて、牛田は水を欲しがる被爆者や避難民で道路はいっぱいになった。そして8月7日頃からだったと思う、牛田町の真ん中にある公園で毎日、毎日、死体を野焼きする光景が続いた。原爆で顔と手に火傷した私は、ヒリヒリする顔と手に家庭用の塗り薬をつけて治療したが、治るのに3週間近くかかった。
私の個人史の、出来事の一端を思いつくまま記してみた。戦後60年、ともかくも平和が保たれたことは、昔の軍国日本のことを考えると、非常に大きな“財産”であり、これからもどんなことがあっても平和を守るため、世界に呼びかけて行くことが、日本の、ヒロシマの使命だと思う。
Copyright(c) HIROSHIMA-NAGAREKAWA-CHURCH All Rights Reserved