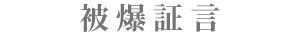

(1937~)
証言日:2013年8月11日
被爆時の年齢:満8歳
被爆の場所:仁保町青崎・爆心地から4.1キロメートル
私の被爆者健康手帳には こう書かれてあります。
私は長い間、被爆者ということを言わないできました。被爆したといっても場所が爆心地から少し離れていたこと、当日自分も家族も誰一人ケガさえしなかったこと、本当に悲惨な目に遭われた人に比べて、私は被爆者と言えるかと思っていました。でも、あることをきっかけに語りはじめました。
第2次世界大戦が激しくなって来た小学校3年生の春。当時海軍大佐で呉海兵団の機関長だった私の父は、警戒警報が鳴るたびに海兵団から迎えの車が来て連れていかれ、母子だけの心細い生活でした。
東洋工業(現マツダ)に隣接していたわが家は建物疎開で壊されることになり、級友は県北のお寺へ集団疎開していく中で私は家族と共に親戚を頼って西条(現東広島市)へ疎開することになりました。
1945(昭和20)年の夏、ようやく転校先の小学校に慣れ、田舎での生活になじみはじめた頃、母が体調をくずして入院し、姉と私は向洋の祖父母の家に預けられることになりました。
8月6日の朝、朝から蝉の鳴き声が激しく、よく晴れた、いかにも暑くなりそうな日でした。祖父母の家で朝食をすませた私は玄関脇の小さな部屋で本を読んでいました。祖父母は仕事に出かけて、その時家にいたのは叔母と姉と私でした。第一県女の3年生だった姉は、その頃学徒動員で専売公社に行っておりましたが6日の朝は腹痛のため休んで奥の座敷に寝ていました。叔母は風呂場で洗濯をしておりました。8時15分、突然の閃光。それはまるで太陽が落ちてきたかのような光。少し間が空いてドカーンと、それはそれはものすごい爆発音。無我夢中で私たち3人ははだしで外へ跳び出しました。玄関前の道から北西の空を見上げると大きなきのこ雲が見る間にモクモクと黒くふくらんでいきます。何の物音もしません。一体何が起こったのだろう、これからどうなるのだろうという無気味さにすくんでしまいました。おそるおそる私たちは家の中に入ってみました。姉が寝ていた座敷の天井は落ち、家の中はモウモウと砂けむり。私はすっかり忘れていたのですが、何年か後になって叔母が話してくれたことがあります。
原爆が落ちる直前、本を読んでいた私が「おばちゃん、のどがかわいた。お水ちょうだい」といったらしいのです。叔母は小学校3年生にもなって、お水ぐらい自分で飲みに行けばいいのにと不満に思いながら台所に入った瞬間に閃光が走ったようです。あとからお風呂場に行ってみたら北側(広島の中心部方向)の窓ガラスは粉々にこわれ、叔母が洗っていた洗濯物はガラスだらけだったそうです。「あの時そのままお風呂場にいたら私は全身にガラスが刺さっていたと思うの。瑞ちゃんは命の恩人なのよ」と叔母は言っていました。
その後、帰って来た祖父母や近所に住んでいた親戚の者、みんなで近くの防空壕に逃げました。午後になって、どうやら広島の街に大変な爆弾が落ちたらしいということで子ども達をこのまま置いていたら危ない、とにかく疎開先の西条に帰らせようということになったようでした。山陽本線が海田市駅で折り返し運転をしているらしいということで叔母に連れられ姉と私は海田市駅まで歩きました。
でも、姉と私が汽車に乗れたのは外がすっかり暗くなってからでした。ギュウギュウ詰めの満員列車、もちろん座れません。子どもだった私は、私のすぐ目の前の人しか見えません。その男の人は上半身裸・体が真っ黒でした。首に、これも真っ黒に汚れたタオルをかけ、泣きながら生のじゃがいもをかじっていました。夜遅く西条の疎開先にたどりついた姉と私は、両親のいない家に2人っきりで布団を敷いて心細くやすみました。この日、軍の仕事で大阪に行っていた父は広島に新型爆弾が落ちたと聞き、心配しながら夜半に帰って来て、寝ている私たちを見て大きく胸をなでおろしたということでした。
私たちが身を寄せていた親戚の伯父の1人が行方不明になっていました。数日後、担架に乗せられて帰って来ました。やけどをしていました。「あぁ、やっと帰って来た」と伯父が肩で大きな息をしたのを覚えています。でも、その伯父も何日か後には息を引き取りました。火葬した時、火傷をしていた足の骨が黒くなっていたのを子ども心に覚えています。
その後、何日かたって再び祖父母の家に行った時、私たち姉妹が疎開するまで通っていた青崎小学校の前を通りました。それはそれは、とても異様な匂いがして走って通り抜けました。祖母に聞きましたら、「原爆で亡くなった人をたくさんリヤカーで運んで来て校庭で焼いたのよ」と教えてくれました。
原爆が落ちた当日には死を免れた姉でしたが、自分の学校や級友が心配で早くに入市しました。その放射能の影響か、ずっと体調がすぐれず、特に季節の変わり目には調子が悪く入退院をくり返していました。とうとう57歳の時、胃癌で亡くなりました。姉が亡くなった7月12日の明け方、母と私はうす暗い中、原爆病院の裏口で葬儀社の車を待っていました。私たちはその1カ月前に父を神様のもとに送ったばかりでした。クリスチャンであったはずの母ですが、この時は「神も仏もあるものか」と座り込んで顔をクシャクシャにして泣いていました。
姉がまだ生きていた時のことですが、ある時、私が備前焼の花びんにお花を生けようとしました。それを見た母は、あわてて私の手から花びんをひったくり押入れの奥深くかくしました。その備前焼は、あの原爆投下直後の広島の街の色と同じで、入市して見た、その時のことを思い出すらしく姉は嘔吐が始まって大変だったようです。姉が生きている間、私の家では備前焼の花びんは押入れの奥深くかくされ、決して出すことはありませんでした。
私が被爆体験を語りはじめたのには2つのきっかけがあります。その一つは、孫がまだ幼稚園の時、何気なく「おばあちゃん、きのこ雲を見たの」と言ったら、「えっ?おばあちゃん、 きのこ雲見たの?百合も見たかったなぁ」と言いました。とてもあわてました。「知らないということはこういうことなのだ、やはり知らせておかなくては」と思いました。私がきのこ雲を見た小学校3年生になったら必ず原爆資料館へ連れて行こうと思いました。その後、孫は小学校でしっかり平和学習をさせてもらったようで、ある時「百合、原爆資料館へ行った?」と聞きましたら、「おばあちゃん、私たち広島の小学生よ。そんなこと当然でしょ」という口ぶりで少し安心しました。その後、広島女学院に進学し中2になった夏、宿題だから被爆体験を聞かせてほしいと言って来て、初めて詳しく話すことができました。
語り始めたもう一つのきっかけは、私の幼稚園の卒園生の1人が2012(平成24)年8月6日平和記念式典で子ども代表として誓いの言葉を読んだことでした。その中に「つらいできごとは同じように体験することはできないけれど、私たちは想像することによって共感することができます。悲しい過去を変えることはできないけれど、私たちは未来をつくるための夢と希望をもつことができます。平和は私たちでつくるものです」。彼のこの言葉を聞いた時、経験していない人には言葉で言ってもわからないと思わないで、話さなければと思うようになりました。
被爆した人が年々少なくなって話を聞いた二世・三世が語り始めている今、きのこ雲をこの目で見た者の責任として、このことはきちんと次世代に伝えていかなくてはと思い始めました。2012(平成24)年広島流川教会でお話したのをきっかけに、2013(平成25)年から東京の女子学院、また3年前から横浜のフェリス女学院の生徒に話す機会をいただき、また幼稚園の子どもたちにも私自身の被爆体験を話し平和の大切さを訴えるようになりました。
Copyright(c) HIROSHIMA-NAGAREKAWA-CHURCH All Rights Reserved