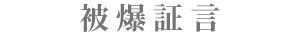
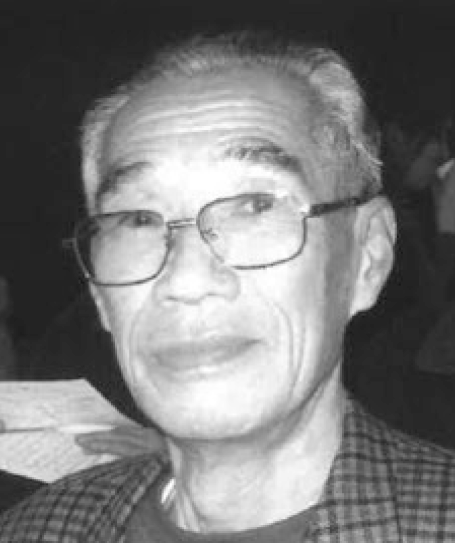
(1931~2012)
証言日:2011年8月14日
私は尾道市の土堂町という所で産声を上げました。父が造船所の仕事をしておりまして、職人を20人ばかり雇っており、小学校の6年間に3回も住所を変えております。それは造船所のある広島県の御調郡向島町、長崎県の長崎市、もう一つは広島県の因島市。3回も住所を変更しましたが、小学校の5年生の時に母が亡くなりまして、長崎県の母方の祖母の家へ預けられました。1942(昭和17)年に因島市に居りました父は、召集をされまして、満州へ行っておりましたが、1944(昭和19)年に父は病気のため満州から帰って来て、私を迎えに来てくれ、私は広島にまいりました。
広島市立第一国民学校(現在の段原中学校)高等科の1年生として転校することが決まりました。父は東洋工業(現マツダ)に入りまして、自動車製造の板金工として自動車を作っておりました。東洋工業の端っこの方にあります小磯町の社宅に住んでいました。学徒動員で、1945(昭和20)年に東洋工業の軍需工場へ行くことになり、土曜日も日曜日もなく汗を流しておりました。そこでは三八式の歩兵銃の銃身を作っておりました。東洋工業は片っぽでは自動車を作り、兵器工場では兵器を作っておったのでございます。
その学徒動員の中学生に夜勤をさせたらどうかということになりいっぺん試してみないといけないということで、近くの生徒に夜勤をさせるということになりました。私は東洋工業と地続きの社宅に居りましたものですから、私ともう1人の 2人が選ばれまして、夜勤をすることになりました。
8月の5日の夜の8時から翌6日朝の6時までが夜勤の時間でした。その日は父も夜勤に入っており、父が「酒の配給があるから、酒の配給を売店でもらって帰ってくれ」と頼まれ、引換券をもらって夜勤に入り、朝の売店が開くまで待っち、酒をもらって帰って「ただいまー」と玄関に入って、父が「なんじゃい」と起きて来た途端でございます。青い光があって、すごい大爆発の音が聞こえました。
「あれ、東洋工業の熱処理工場か何かが爆発したんじゃないか」と思いました。社宅の窓という窓、ガラスは全部割れてしまいました。表側にある部屋の天井が落ちてまいりました。その中で父は私の声を聞いて立ったんだと思いますが、指から血が流れております。どうしたんだろうと思い見ましたら、父は胸に手を当てており、その胸に割れたガラスが刺さっており、どんぶりに3杯くらいの血を吐きました。私はびっくりして、近所の人にそのことを話ましたら、隣の老人が自動車で東洋工業の病院へ運んでくれまして事なきを得たということでございます。
私は帰りに、異様な光景に会いました。出くわした人は全身が火傷で、男女の区別も年齢も分からないほど、髪の毛は焼け縮れて顔は灰塵と汗で真っ黒に。皮膚は顔、胸元、両手からむけて垂れ下がったままで、血まみれになって、眼だけがギョロギョロとしておりました。みんな行く先もわからず、逃げてきた多くの被爆者たちでした。
帰り着くと、町内会長から「青崎国民学校に行くように」と言われて、そこへ行きました。もうお昼を過ぎておりましたけれども、そこは仮の診療所になっており、命を取り留めた多くの人々が溢れておりました。講堂は被災者で足の踏み場もないほどです。兵隊さんがおられ、私に「学校の近くの山に掘られた東洋工業の防空壕へ行って、菜種油をもらって来い」と言われました。そこへ行って菜種油の入った四斗缶を二ついただき、手押し車を借りて国民学校へ帰りました。講堂はほぼ全員が火傷の方々ばっかりでしたので、火傷薬もほぼなくなっていたので、四斗缶の菜種油を火傷の薬としてつけるということでした。菜種油がなぜそこにあったのかというと、金属の機械加工に潤滑油として必要な油で、特に銃身の芯の穴を開けるのにはこの油がないと機械が焼け付くので、鉄砲の加工には必需品でしたので、東洋工業が防空壕まで掘って埋めて保存をしておったわけです。
油を持ち帰って講堂へ行きましたら、あちらこちらから喉が渇いたのでしょうか、「水を、水を」と言う人がたくさんおられ、私は飲ませてあげようかなと水を探しましたが、近くにはありませんでした。なぜかと言うと火傷をした人に水を飲ますのはよくないんだそうで、看護していた人から「むやみに水を飲まさないように」ということで、あった水を隠してしまったということでした。そういうことで、私も聞こえぬふりをして他の仕事をしておりました。
家族の名前を呼ぶ人もたくさんいらっしゃいました。でも、それを聞いても連絡をする方法がないんです。電話がまずない。つながっておりませんでした。これもまた聞こえぬふりをしておりましたら、兵隊さんが「ここにいる中にもう死んだ人がおる。その人を探せ」ということになりました。そして亡くなられた人の胸の所に紙を置いて行くことになり、亡くなられた人を探す仕事をずっとしました。ですから火傷をした人、あるいはそうでない人もいましたが、もう息途絶えた人が講堂にいっぱいになっておりました。夕方までに本当に多くの人々が亡くなってしまいました。
それから少しして、兵隊さんから「校庭に焼き場を作るから手伝え」と言われ、校庭の隅の方に、焼き場というよりも穴を掘りまして、そこに薪をうず高く積んで、火を点けました。東洋工業の防空壕の中には毛布がたくさん積んであったので、その毛布が講堂に敷いてあったんですね。その毛布を二つに折って死んだ人を乗せて校庭へ出て、火が燃える所へ人間だけをドンと落とすというのをずっと繰り返しておりました。本当に1日に何十人という人を、そんなことを言ったら申し訳ないのですけれども、何かをくべるような感じで仕事をしてまいりました。
6日はそれで過ぎまして、7日もそれをやりました。ところが、7日に社宅の裏の筋の人が、
国道2号線のルートか、あるいは大内越峠を通って行くルートか。それ以外にも反対の方、横川の方に行くルートもありましたが、あっちの方には行ってないだろうと。中町からあっちの方へ行くためには火の燃えている中を通って行かなければならないだろうと。で、国道2号線をたどったとすれば自分の家に帰る道だから、大内越峠ルートだろうということで、何人かの人がその道中を写真を持って「こんな人がここを通らんかったか」と尋ねて歩きました。馬木の国民学校にそういう人が行かれたはずだということで、8月8日に父方の親類の家に大八車を借りに行き、近所の人と一緒に彼女のお父さんとお母さんも連れて、馬木の国民学校へ行くと、そこにお嬢さんがおられたのです。足のすねの膝の下あたりをえぐり取られていて、よくもこんなになっておるのに、馬木の学校まで歩いたなというくらいにひどい傷でした。大八車に乗せて向洋の方へ帰り、東洋工業の病院へ連れて行って預けてまいりました。
国民学校高等科の生徒は、学徒動員でほとんどが軍需工場に行っておりました。私たち第一国民学校の生徒も先ほど申しましたように、東洋工業へ行っておりましたけれども、もうその当時は鉄砲を作るよりも、建物疎開の方が忙しいということで、鶴見橋の付近の建物の疎開に駆り出されておりました。生き残った同級生は3人だけでございます。私と、一緒に夜勤をした者と、それから当日病気をしたのかで休んだ者、この3人です。したがって、卒業証書もなく、学校も壊れて焼けており、同級生もいないということで、同窓会もありません。
話をする人もいなくなった、そんな中、1946(昭和21)年、広島流川教会の門をたたきました。谷本清牧師にいろいろ教えを被って、幼稚園の園舎を建てるために裏の方の整理をお手伝いすることにいたしました。私の背よりも深く埋まった大きな石があったり
教会はそういうような形で、谷本清牧師が努力をされ、あるいはその当時の教会員がいろいろとお手伝いをして復興したということです。もう、これ以上しゃべると、当時を思い出して胸がつまってきます。
谷本清牧師の著書『広島原爆とアメリカ人』は、「ある牧師の平和行脚」という形で出ておりますが、第1章の3節に「一牧師のビジョン」で書いておられる一節があります。「教会を必ず復興する。説教は愛の業によって裏付けされなければならない。そのために平和運動に務める」と。「私はこのビジョンをひっさげて役員会を招集し、今後このことに邁進したいから協力を願う」と訴えたそうです。役員たちも賛成し、協力を誓ったということでございます。それで、教会が復興することができました。私たち教会員はこの「説教は愛の言葉によって裏付けされなければならない。そのために平和運動に務める」ということを心にとめて、この教会をもっと平和の源になる教会にしていきたいと今も思っております。
Copyright(c) HIROSHIMA-NAGAREKAWA-CHURCH All Rights Reserved