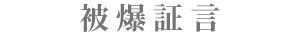

(1929~2016)
証言日:2010年8月15日
8月6日広島、8月9日長崎に原爆が落とされ、アッツ、グアム、サイパンの玉砕、そして9日はソ連が参戦し、本当にどうなるのだろうと思っていましたら、14日に「明日は玉音放送があるから絶対に聞くように」という通達が回ってきました。そして15日に、ピーピーガーガーいうラジオを叩きながら一生懸命難しい言葉の天皇陛下のお言葉を聞いて、ポツダム宣言を受諾したことと、戦争が終わったんだなあという気持ちがしました。だけど、私たちが今までやってきたことはいったいどうなるんだろう。どうしたものだろうかと、なんか気落ちがしたような感じでした。
原爆のことをお話ししたいと思いますけれども、その当時の学徒がどういう生活の毎日を送っていたかということを、先に少しお話ししたいと思います。
私たちは終戦の年が15歳で、女学校2年生の時はまだ授業がございました。ですけど、「英語は廃止」ということになり最も楽しいはずの音楽が最も面白くない授業で、ハニホヘトイロハということになって、それで、ちょうどその頃「カルメン」を歌っていたんですけど、無伴奏で1人ずつ出席簿を見ながら先生がピックアップしていかれるわけですね。家にピアノとかオルガンがある人はちゃんと歌えるんですけど、家にない者は「へ、ヘ、ヘト、ヘ、ヘ」とか言って、音楽の先生が「もうよろしい」というようなことで、ちっとも面白くなかったんですね。それで私たちは一策を考えて、そのころ学校農園というのが田中町にありまして、肥料がいるので、
出征兵士の留守宅に稲刈りとか麦刈り、田植えにも行きました。専売公社へ兵隊さんの煙草も作りに行きましたし、糧秣支
そうこうしているうちに、被服支
だんだんだんだん布もなくなって、戦地から血がついた軍服が返ってきました。それのボタン付けなんかをしたんですけれども、それもなくなって、1945(昭和20)年の5月1日から、東洋工業、今のマツダへ転属になりました。マツダでは菜っ葉服って言ったらみなさんはお分かりになるかどうか、上下の草色のスフの作業着を着せられて、そしてリーマーという銃身を磨くんですね。もう胸から油だらけになってそれを磨いて、そして磨き終わった物をコンコンと叩くんですけど、それが、工員さんなら分かるんですが、私たちには分かりませんから、みんなが「銃身を磨いたけど、この弾はまっすぐ飛んでいくんじゃろか」と話をしたりしていました。
東洋工業に行っている中から80人ほど、暗号電報を打つために沖縄に行かされることになりました。今考えたら、沖縄は4月から6月にはもう大変なことになっていたのに、まだ日本は戦争をするつもりだったんでしょうか。
東練兵場に第二総軍司令部があって、そこで訓練を受けました。第二総軍司令部へ行く者は、8月6日は特別休暇で、私は郊外の可部におりましたので、助かりました。市内にいた者は亡くなりました。あれだけ離れている可部でも、稲が、まだ穂が出ていませんでしたけれど、ピカッと光った瞬間に、バサーと横になりました。ドカーンといった途端に、武田山という山にモクモクときのこ雲が上がり、その中からパラシュートに四角な箱がついたものがどんどんこっちへ流れてくるので、「いったいあれは何だろう」と思っていたら、私の家から100メートルくらいの所に落ちたんです。「あれは時限爆弾かも分からんから」と言って、各家に「毛布を窓へ貼れ」と通達があって窓へ貼りました。だけどそれは何でもなかったようです。
これは大変なことだと思って私はすぐに警察の所まで走って行ってみましたが、トラックが着いて、それがみんな目の玉の白いところが真っ赤で、みな手をこうやって、皮膚が垂れて、包帯をしてる人は胸の皮膚が全部下がっているんですね。「これはひどい。何があったんですか」と聞いたら「上柳町に爆弾が落ちた」という人がいるかと思えば、「そうじゃない。とにかく広島は大ごとじゃ」という人もいました。そして可部のお寺とか学校とかが収容所になりました。しかし、どんどん死んでいくので焼き場が足りなくて、山のすそ野の所でゴーゴーゴーゴー燃やしていました。その時もB29が上空を飛来していました。
私は7日の日が第二総軍司令部の出頭の日だったので、横川まで電車で来たんですけれど、電車が横川の手前で停まって、電車の天井はハエが真っ黒にたかっていました。そこをずっと通って今の十日市あたりで、人間を積み木のように重ねて、灯油をかけて焼いているのを見ました。いたるところで、水道管が破裂してそこに真っ黒くなった人が突っ込んでいました。八丁堀まで来たときに、畳一畳くらいの防火槽が二つあったんですけど、それにみんな折り重なるように突っ込んでいました。でもそのころはもう死体を見るのもなんともなくて、そして第二総軍司令部へ行くことだけが頭にあったんです。友だちが行かないと言うのに私はくそまじめだったのか、1人で行ったんです。東警察だった今の広銀の銀山町支店の稲荷橋は横木だけが残っていました。それを渡って東照宮の所を通って第二総軍司令部へ行きました。東照宮の前には男か女かわからない人が座っていました。第二総軍司令部に行きましたら、昨日まで私たちを訓練してくださっていた中尉殿は、もう遺骨になっていました。「学徒は学校に先生がいらっしゃるはずだから、学校へ行きなさい」と言われて、戻ったんですけど、先ほど東照宮の所へ座っていた人は横に転がっていました。
そして焼野原の中を歩いて
私たちも学校の後片付けとかをいろいろしましたけど、9月の半ばになって、なんとか学校も再開ということで、いよいよ勉強の準備をしようかという時に、机も椅子もありません。そうしましたら、大竹の潜水学校から、机と椅子がくっついたのを送ってくださったんですね。草津の港から、大きい者は2人で一つ、小さい者は3人で一つと、草津から今の皆実高校まで3度運びました。9月の暑い暑い日でしたけど、でもやっぱり、勉強ができるんだという喜びで、みんな一生懸命文句も言わずに運びました。なんとか戦争も終わって普通の授業というか、安心できる授業ではありませんけど形になったものになりました。そして長い長い戦争が終わって、私たちもやっと落ち着いて生活できるようになりました。
私は今、神様に守られて幸せに健康に暮らしていますけど、これから先召されるまで一日一日を大切に生きていきたいと思っております。どうもありがとうございました。
Copyright(c) HIROSHIMA-NAGAREKAWA-CHURCH All Rights Reserved