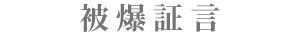

(1909~2012)
証言日:2010年8月8日
命永らえてこのような話ができますこと、誠にうれしいことと思いますが、いい具合にお伝えできますかどうかちょっと心配なこともあります。
まず、私がどの辺に住んでおりましたかということから始めます。爆心地から2、3キロメートルのところの牛田町で、町内でも当時は丹土区といっていた地区でした。水源地が近く、京橋川にもけっこう近く、静かな田園風景に囲まれた家でございました。
その時に家に居りました者は、私と次女の6歳になる娘と、生後4カ月の末っ子の3人です。主人は、今は郵政局になっておりますが、白島終点の所にあります役所に勤めておりました。ないことに、その晩は宿直でした。そんなこと今まであったと思いませんのですけど、家におりませんでした。長男は中学の2年生で、学校から己斐の方の山にある製缶工場へ行っておりましたから、朝早く家を出ました。そして、長女は小学校から集団疎開して、三次の奥の方へ行っていました。
私は、朝早くから風呂場で洗濯をしておりました。当時は、洗濯機はなかったので木のたらいで洗濯します。6歳になる娘はどうも玄関の門の所にでもいたんじゃないかと思うのですが、その何ともいえない音、私はどうしてもその音が思い出せないんですけど。びっくりした気持ちだけが思い出されるんです。娘が台所に跳んで帰りまして、2人で、寝ている赤ん坊の所に跳んで行きました。
その時はガラスもなにもなかったと思うんですけど、奥の八畳の部屋に、雨戸もみな開けまして、涼しいように縁側の近くの方の畳に寝かしておりましたら、それが布団と一緒に中央よりまだ奥の方に飛ばされておりまして、これはまあ大変なことだと、赤ん坊をちょっと抱き上げようと思いましたら、私の右の手が動かない。たらいの縁に手がかかっていたので、その瞬間に折れたらしいです。そのことは後で気が付いたんですけれども、どう手が折れたか、その時には考えもしませんでした。抱き上げることもできず、眺めましたら天井が裂けて、木がぶら下がって、たたんでいたおしめが部屋中に散らばっていました。窓という窓が全部なくなり、道路の方も大手が全部なくなり人が通るのが見えました。しばらくしますと、人が山の方に逃げて行くのが畑の方の窓から見えます。「ああ、逃げて行かれるなあ」と思いましたけれど、どうすることもできませんので、困っていましたら、近くにいる懇意な奥さんが来られて、天井板を割いて手に当てて、おしめで包帯の代わりに巻いて首につってくださいまして、まあ助かりました。
それで、さあ、どれぐらいの時間が経ったのか、今考えてもわかりませんですけれど、道路を見ていましたら、上半身裸で濡れたようなズボンの男の人が通りかかりました。ふっと横顔を見たら谷本清先生なんです、広島流川教会の。びっくりしまして「先生」と声をかけたんです。先生が「おお」と言って寄ってこられて。「先生、どうしてこんな所を通られるんですか」と言いましたら、「己斐の方におったのに、橋がなかったから泳いだ」っておっしゃるんです。どの辺を泳がれたのかちょっと後からではわかりませんけど、「大方流された。命が助かってやっとここまで来たのよ」と言われまして、もうびっくりしました。その時とっさに私が見ましたら、川の方から煙が、家が焼けてくるのがわかりまして、先生から預かっていました聖書、讃美歌があったものですから「先生、持って帰ってくださいますか」と言ったら、「ああ」と言われまして。
どうしてその聖書、讃美歌を私の家が信者でもないのに預かっていたかといいますと、ちょうど8月2日に主人の甥が交通事故で亡くなって。主人の弟は牧師でしたので、その時はもう亡くなっていましたけれども、子どもは全部広島へ引き取っておりまして、その子が死んだものですから3日の日に広島流川教会の先生にお願いして、主人がお葬式をしました。その時に先生が「牛田は大丈夫だろうから、これだけ持って帰ってください」と言われて、風呂敷包みにして、かなり大きかったですが持って帰って、私は大事に押入れの奥の方にしまっておきました。それがついこの間の3日の日ですから、「ああ、これは大変だ。先生にお返しする方がいいな」と思って、先生も「いいよ」って抱えて帰られました。
後に先生は随分ご苦労なさり、私は長い間ご一緒しましたのに、あの時の話とか、いかに先生が活躍なさったかとかいうようなことは一度も話したことがありません。私もどういうわけでしょうね、一度もどういうふうに生きてきたかということは、一度も話したこともありませんでした。亡くなられてから書かれたものなどを見ますと、先生も大変だったなと今頃になって、つくづく思います。
そうこうしておりますと、家が焼けはじめ、近所の者が5人ほど集まりまして「逃げた方がよさそうだ」「やっぱし逃げるなら山かなあ」と言って。ちょうど後ろに工兵の作業所がありましてね、水源地の前ですが、その続きに見立山って低い山があるんですが、そこへ逃げることにしました。一升瓶へ水をいっぱい入れまして、主人の大きいこうもり傘を持って、子どもを連れて歩いて逃げました。入り口は1カ所で、兵隊さんが鉄砲を持って立っていました。そこを通過しないと入られません。たくさんの人がずらーと並んで山の3分の1か4分の1ぐらいの高さの所に割り込みました。時間が経つとだんだんとすごい人が入ってきました。上半身裸で、焼かれて、顔も黒くなったような人もだいぶ入って来ましてね。主人と長男がいつ帰ってくるかなとそればっかりで、その兵隊さんの立っている場所を見つめていました。だんだん目が痛くなって、「ああ、これは帰って来ないかもしれないなあ」と思うようになりました。
そうすると、夕方だったと思うんですが、白い包帯をした長男が帰ってきました。大急ぎで皆で一緒に家に帰ったんですが、その時はもう広島市内の方は真っ暗になっており、煙で何にも見えませんでした。
家に帰り着きましたら、長男が「お父さんが帰って来ないのなら、僕が見に行く」と、その場ですぐにどこかへ出て行きました。まあ、長い道を帰ってきたばかりなのによく行ったなと思いました。ですが、薄暗くなって「どこにもいません」と帰ってきました。
日は暮れてきますし、ちょうど家の前に少し空き地があったものですから、そこへ、私が蚊帳を持ち出しまして、どなたが立ててくださったのか、棒を2本ほど立てて、蚊帳は斜めに置いて、そこへ子どもたちを入れました。親は外で夜明かししたんですけど、5軒の内3軒は主人が帰って来られたと思ったんですが、後でわかったんですけど、2人は即死で、1人は2日目くらいに帰って来られたそうです。
昼や夜は何をいただいたか私自身は覚えませんが、当時6歳の娘に「昼はどうだったかね」と聞きましたら、「山で乾パンを配られた」と言うんです。「私乾パン食べたよ。ご飯は食べなかった」と言うんです。「いい具合に寝られた?」と言うと、「蚊帳が顔をさすって寝られなかった」と。それは65年も経って初めて聞く話で、いままでそういう話は全然しなかったですから、ああ、そうだったのかと思って、夕ご飯もいただかずかわいそうなことをしたなと思いましたが、食べる物はなかったですからね。朝、食事したお釜の中が
その晩はそのまま外で過ごしまして、あくる日に荷物をまとめて父の家に逃げることにしました。父は5、6分行った所に、4年前の1941(昭和16)年に牛田は大丈夫だろうと思って家を建てたんです。そこに居りましたので、そこへ荷物を運びました。聞きましたら、父は私の家を見に来てくれたらしいんです。血が石段にあって、家の中に誰もいないからいい具合に逃げたなと思って、家に帰ったそうです。そうこうするうちに火事が広がり、父の家の1軒先で風向きが変わって助かったんです。向かい側の斜め前の大きなお家は門だけ残して全部焼けました。そこへ私らはかけ込んで、荷物をどういうふうに置いたか、私は手が片方利きませんから長男がみんなしてくれたんだろうと思うんです。
そこに着きまして、あくる日、主人が帰って来ないので、長男と父とが、「死んでいるに違いない。見に行ってくる」と2人で出かけました。夕方遅くに帰って来て、「たくさんの死体を見たけれどもいなかった」と言いました。「夕飯は僕、いらない」と長男は言い、そのまま休みました。とてもご飯が通らなかったんでしょう。後で考えると、見に行かなかったら2人とも命はあったような気もします。
それから3日目と思うんですが、郵政局の逓信病院が再開されたということで、「じゃあ、私も手を診てもらいに行きます」と言って行きましたら、もうたくさんの人でした。行列に並んでまして、だんだんとこう近づいてきましたら、廊下の一部を開けてそこから入るようにしてあったらしいんですが、その廊下の両方に、死んだ方がずらっと、頭をこちらに向けて寝かしてありました。びっくりしました。休んでいたと思って 見ていたんです。そうじゃなくて死体だったんです。ほんとにどうしようもないと思いました。ひょっと見ましたら、私の足元に白衣を着た人が寝ていました。この人は山で私の隣で「水をくれえ」と言われた人だったなあと思い、本当に気の毒でした。ご飯茶碗の底に黄色い液がありましたから、横向きになって、吐かれたのではと思いました。
ようやく順番が来ました。蜂谷先生の診察室の右側には、たくさんの人がいました。左側には兵隊さんのような方が全身黒焦げで、裸で大の字になって死んでいました。目がクリッとして恐ろしい顔でした。これは大変なことになったと思いました。足元にも1人横になって死んでいました。私は手ぐらいのことで先生に診てもらうことはないと思って大急ぎで帰りました。
どう帰ったか道もわかりませんけど、神田橋にかかりましたらね、ちょうどそのとき満潮でね、死体がたくさん上がっていました。プワプワ、プワプワ上がってくるんですがね、みんな手足が膨れて、もう衣服は脱げています。頭は全部髪がふわーとして、顔を下に向けているので、ひょっとしたら主人がいるんじゃないかなと見ましたけど、分かりませんのですよ。膨れているのと、裸なのと両方で、見分けがつきませんでね。次から次にふわーと上がってくるのに恐ろしくなって、飛ぶようにして帰りました。
それからどういうふうに日が経ったか覚えませんけど、ちょうど1週間目に役所の方が2人来られて、主人の亡くなった所がわかったから今からお骨を掘りに行きましょう声をかけてくださって、一緒に行きました。場所は今の並木通りは川になっていて、福屋の向うに幅がわりに広い、石垣をついた川が流れていました。右側に錦水旅館という旅館があったんです。私は知りませんでしたけど、郵政局の指定旅館だったそうです。そこで「ここで亡くなったんですよ」と言われてびっくりしましたね。正反対の所ですからね。よく聞きましたらね、ちょうど部長さん夫婦と子どもさんとが着任されて、主人は朝帰るところですから、ついでに案内してあげようと思ったんじゃないでしょうかね。くわしいことはわかりませんけれども。無論その方も坊ちゃんもみんな亡くなりましたけど。
不思議なことに、きれいに整地したようなかなり広い黒っぽい土がある所がありました。おかしいなあ、ここに何かありそうなものと思いました。あちこち掘ってみましたけれど、なんにも出てきません。もう出てこないから帰ろうかねえと言って、「もうちょっと、もう1カ所掘ってみましょう」と言って、道路に近いところだったと思うんですが、さあ、なんぼくらい掘ったでしょうかね。30センチメートル、50センチメートルも掘ったか、ちょっとよう覚えませんが、かなり掘りましたら、こんな小さい時計が出てきました。「ああ、ここで誰か死んだんだな」と。
そしてまた掘ってましたら、これぐらいの金具の鍵が二つほど出て、それを掘った人が「ああ、郵政の自転車の鍵だよ」と言われて。ああ、じゃあ主人は自転車に乗ってここへ来たのかなあ。でもそれは誰の鍵かわかりませんですから。そしてもう少し掘ってましたらね、財布のがま口の金具が出てきました。ああ、これ、主人の財布の金具に違いないと私は思いました。やっぱりここで亡くなったんだなと思って、そのまま帰りました。家へ帰って母に聞きましたら、山梨県の人ですから、「あ、私がお土産にあげた印伝の財布よ」って言われました。ああやっぱり、主人があそこにいたんだと思って、何日かしまして、お墓に骨の代りにそれを入れました。なんぼ掘っても骨は全然出てきません。どなたのも骨らしいものは一つもなかったです。
そうこうしているうちに長男が、気分が悪いと言い出しました。島根県の農家の親戚が、「自分の家で養生した方がいい」って連れて帰ってくれました。島根のお医者さんが「病名がどうしても分りませんから、広島へ連れて帰って、いい先生に診てもらいなさい」と言われたので、年が明けて連れて帰ったと思うんです。長男が帰った時は元気だった父は、3月8日に亡くなりました。蜂谷先生に診てもらいましたら、「少し輸血しようか」と言われるんで、私が3回ほど血液を提供したと思います。最後に「あんな痛いことはもういいです」と息子が言いますんで、「それじゃもう、やめましょう」と。ところが6月だったと思うんですが、半紙半枚の通知を、持ってきてくださって、読んでみましたら「白血病で回復の見込みがないから、見舞金をあげます」って書いてあるんです。千円ですね、見舞金は。ほんとになんて言っていいか、腹立たしいし、情けないし、何とも言えない気分でした。それから2カ月して、8月2日に亡くなりました。結局わが家の男性は全部亡くなったわけです。
本当にどうしようもないありさまでした。家の屋根は飛ぶし、窓はないし。家の荷物を出した時に、見知らぬ方が子ども3人ほど連れてね、「行くところがないからおらしてください」って言われたんですよ。「いいですよ。どうぞおってください」ってその人におってもらいました。
そのうち、9月になってから、疎開していた長女も帰って来ましたので、狭いし、父の家もたいへん傷みましたからね。4畳半にみんな住むんですから大変でした。蚊帳をつって、私は箪笥にもたれて寝たのを憶えています。で、家に帰ろうということになって、親戚の者がちょっと直してくれまして、家へ帰りました。
それからは大変な人生が始まりました。神様からみんな智恵をいただいているのに、ほんま、悪いことに智恵を働かすなんてとんでもないこと。そうでなくても地球には地震もあり大水もあるのに、そこまでして殺し合うこともなかろうにと常に思っています。最近少しずついい兆しが見えたように思います。私が生きている間にはどうにもなりませんでしょうけど、どうぞいい土地になってくれたらいいと思っています。
Copyright(c) HIROSHIMA-NAGAREKAWA-CHURCH All Rights Reserved